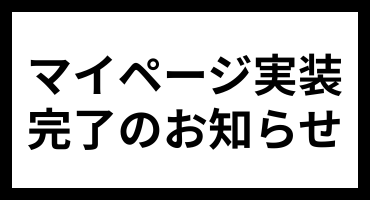当たり前の生活は、決して当たり前ではない
最近、私たちは日常の中で「当たり前」だと思っていることが、実は多くの人にとって当たり前ではない、という現実を改めて突きつけられています。安全に眠れる家があること。
子どもが学校へ通えること。水道をひねればきれいな水が出ること。
これらは私たちにとって日常ですが、世界の多くの子どもたちにとっては「夢」に近い現実なのです。

背景と課題認識
私は昨年から、毎月ユニセフへ少額の募金を続けています。毎月送られてくる冊子を手に取ると、その中に映し出される子どもたちの姿に胸を打たれます。
今月の表紙には、アンマン郊外の難民キャンプで暮らす女の子の写真がありました。346人の子どもたちを含む138世帯がそこに暮らし、ほとんどがシリア難民で、他にもパキスタン、ヨルダン、エジプトから避難してきた家族が少数ながら共に生活しています。ユニセフは教育を絶やさないため、キャンプと学校を結ぶバスを運行し、学びの機会を支えています。その女の子が、夕暮れの光の中で見せた小さな笑顔。そこには「生き抜く力」と「未来への希望」がにじんでいました。
この現実を知ると、私たちの暮らす世界は決して均等ではなく、そして「今ここにある日常」は偶然にもたらされた恩恵であることを実感します。
私の信念と未来へのビジョン
私自身、寄付という行為は「ほんの小さな一歩」に過ぎないことを知っています。
毎月の少額の募金で、すぐに世界が大きく変わるわけではありません。しかしその小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな波となり、子どもたちの未来を支える力につながると信じています。
私が大切にしている信念は、「持続可能な世界を次世代に残す」ことです。
そのためには、環境問題や教育、平和といったテーマを、他人ごとではなく自分ごととして受け止め、できることから実行していくことが不可欠です。
私にとって募金はその一つの形であり、同時に「自分自身の生き方を問い直す鏡」でもあります。
未来のビジョンとして描くのは、どの子どもも夢を語れる世界です。
生まれた場所や環境に左右されず、教育を受け、自らの可能性を広げていける社会。その実現に少しでも貢献することが、今の私の使命だと感じています。
私が日々実践していることはシンプルです。
毎月の定額寄付を続けること
届いた冊子を家族や仲間と共有し、現状を一緒に考えること
SNSやブログを通じて、得た気づきを発信すること
これらは大きな行動ではありませんが、「小さな行動を継続すること」こそが力になると信じています。そして読者の皆さんにも、ぜひ自分なりの形で世界とのつながりを感じていただければと思います。募金でなくても構いません。日常の中で「無駄を減らす」「環境を守る選択をする」「身近な人に思いやりを持つ」など、一人ひとりが選ぶ行動が未来をつくります。
アンマンの女の子の笑顔を見たとき、私は思いました。「この笑顔を守りたい」と。彼女の未来は、私たち一人ひとりの選択によって少しずつ変えていけるのだと。
小さな一歩を積み重ねながら、共に持続可能な世界を築いていきませんか。未来を語り合い、そして行動する仲間が増えることを心から願っています。