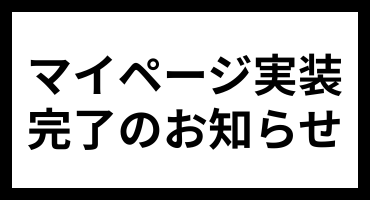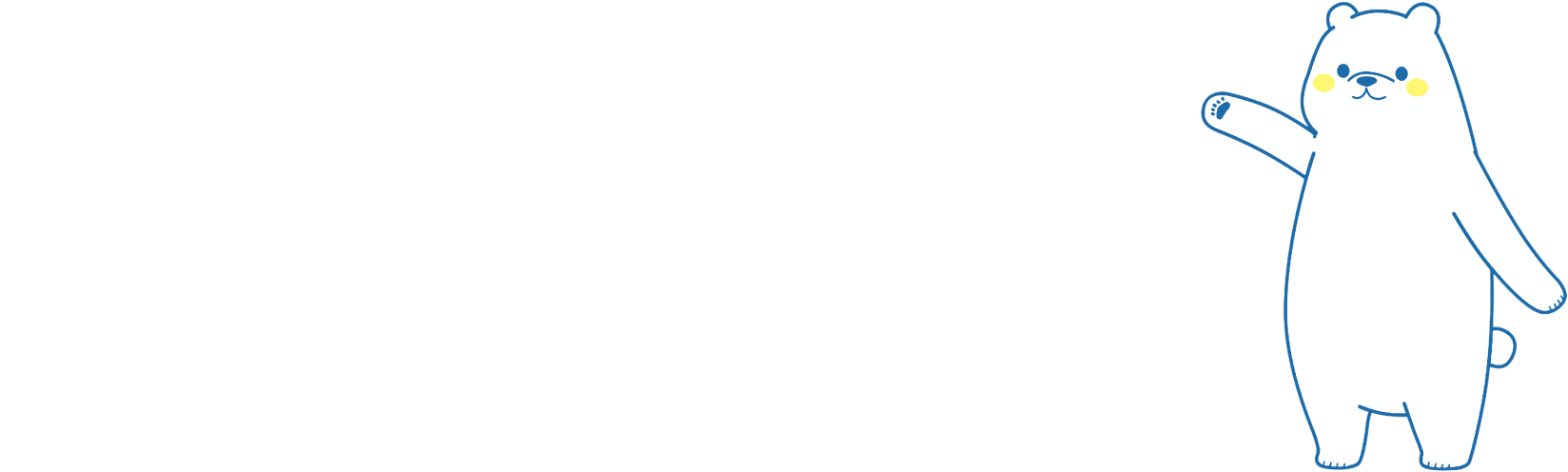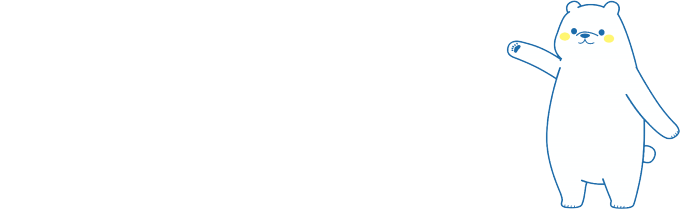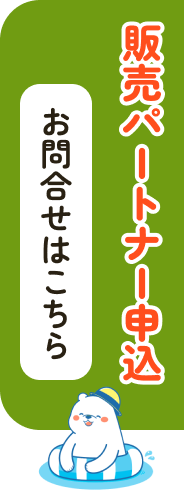よくあるご質問
Carbon Zero Global 株式会社は、持続的にカーボンクレジットを創出する環境ビジネスを展開する企業です。CO₂吸収を行う森林プロジェクトを運営し、継続的にクレジットを生成する仕組みを確立。契約者や企業に安定したリターンを提供し、持続可能な環境価値の創出を目指しています。
ご不安をお持ちの点、率直にご質問いただきありがとうございます。当社は規模としてはスタートアップに分類されますが、その分、誠実な情報開示と丁寧な契約者対応を重視しております。信頼性確保のため、以下の取り組みを行っています。
- 外部法律事務所との顧問契約による法令順守体制の強化
- プロジェクト内容やカーボンクレジット創出状況についての定期的な進捗報告
- 契約者向けマイページ機能を導入し、2025年11月27日より公開しております。
- ベトナム政府の開発計画・国際認証制度(VCSなど)に準拠した森林プロジェクトの推進
また、万が一プロジェクトがクレジットを創出できなかった場合の「70%買取の保証制度」も導入しており、リスク低減にも取り組んでおります。引き続き透明性と信頼性を重視し、ご期待に応えられる企業であり続けるよう努めてまいります。
- 外部法律事務所との顧問契約による法令順守体制の強化
- プロジェクト内容やカーボンクレジット創出状況についての定期的な進捗報告
- 契約者向けマイページ機能を導入し、2025年11月27日より公開しております。
- ベトナム政府の開発計画・国際認証制度(VCSなど)に準拠した森林プロジェクトの推進
また、万が一プロジェクトがクレジットを創出できなかった場合の「70%買取の保証制度」も導入しており、リスク低減にも取り組んでおります。引き続き透明性と信頼性を重視し、ご期待に応えられる企業であり続けるよう努めてまいります。
弊社は、大規模な常設オフィスを構えるのではなく、機動性と柔軟性を最大限に活かしたワークスタイルを採用しております。これは単なるコスト削減ではなく、「少数精鋭で高い成果を出す」ことを追求した経営判断です。
集中を要する業務には静かな環境を、企画や構想を練る際には開放的なスペースを選ぶなど、業務の特性に応じて最適な環境を整備し、社員の成果の質とスピードを最大化しています。また、クラウド管理やオンライン会議を徹底することで、場所にとらわれず迅速な連携と意思決定を可能にしています。
必要に応じて対面での打ち合わせにも柔軟に対応し、その際は目的に合わせて最適な環境を整え、信頼を基盤とした丁寧なコミュニケーションを大切にしています。
現在は正社員を中心とした8名体制で運営しており、分野ごとに外部の専門人材とも連携。内部のフットワークと外部の専門性を掛け合わせることで、少数ながら高品質なサービス提供を実現しています。
特にご注目いただきたいのは、「少数精鋭 × 自由度の高い環境」により、変化の兆しをいち早く捉え、意思決定から実行までをスピーディに行える点です。
カーボンクレジット市場は、制度や国際ルールが急速に整備されている領域です。このような新しい分野で競争優位を築くためには、スピード感のある判断と実行力が欠かせません。
私たちは大企業にはない“柔軟性”と“俊敏性”を強みとし、他社に先んじてプロジェクト機会を掴み、お客様とともに成果を生み出すことを大切にしています。
「組織の規模」ではなく「どれだけ早く、確実に成果を出せるか」が問われる今の時代において、弊社のスタイルと判断基準は必然的な選択であると考えております。
今後も実直で透明性のある姿勢を貫き、信頼を積み重ねてまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
集中を要する業務には静かな環境を、企画や構想を練る際には開放的なスペースを選ぶなど、業務の特性に応じて最適な環境を整備し、社員の成果の質とスピードを最大化しています。また、クラウド管理やオンライン会議を徹底することで、場所にとらわれず迅速な連携と意思決定を可能にしています。
必要に応じて対面での打ち合わせにも柔軟に対応し、その際は目的に合わせて最適な環境を整え、信頼を基盤とした丁寧なコミュニケーションを大切にしています。
現在は正社員を中心とした8名体制で運営しており、分野ごとに外部の専門人材とも連携。内部のフットワークと外部の専門性を掛け合わせることで、少数ながら高品質なサービス提供を実現しています。
特にご注目いただきたいのは、「少数精鋭 × 自由度の高い環境」により、変化の兆しをいち早く捉え、意思決定から実行までをスピーディに行える点です。
カーボンクレジット市場は、制度や国際ルールが急速に整備されている領域です。このような新しい分野で競争優位を築くためには、スピード感のある判断と実行力が欠かせません。
私たちは大企業にはない“柔軟性”と“俊敏性”を強みとし、他社に先んじてプロジェクト機会を掴み、お客様とともに成果を生み出すことを大切にしています。
「組織の規模」ではなく「どれだけ早く、確実に成果を出せるか」が問われる今の時代において、弊社のスタイルと判断基準は必然的な選択であると考えております。
今後も実直で透明性のある姿勢を貫き、信頼を積み重ねてまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
日本ではカーボンクレジットは一般的に金融商品には該当しませんが、取引の形態によっては金融商品取引法の規制を受ける可能性があります。環境価値の取引として扱われ、税務処理や会計基準によって異なる場合があります。
いいえ、カーボンクレジットの概念自体は1997年の京都議定書で正式に導入され、その後2005年の同協定の発効とともに国際的に運用が始まりました。特に、クリーン開発メカニズム(CDM)が先進国と途上国間のクレジット取引を促進しました。2015年のパリ協定では、より広範な市場メカニズム(Article 6)が導入され、現在はVerra(VCS)、ゴールドスタンダード(GS)、J-クレジットなどの多様な認証基準のもとでカーボンクレジットが発行されています。したがって、新しい概念ではなく、すでに20年以上の歴史を持つ国際的な認証制度です。
カーボンオフセットとは、企業や個人が自らの温室効果ガス(GHG)排出量を削減する努力を行った上で、どうしても削減できない分をカーボンクレジットを購入することで相殺(オフセット)する仕組みです。一方、カーボンニュートラルとは、企業・国・個人のGHG排出量と吸収・削減量を合計してゼロにすることを意味します。例えば、ある企業が1,000トンのCO₂を排出した場合、自社の削減努力に加え、1,000トン分のカーボンクレジットを購入し相殺することでカーボンニュートラルを達成できます。
カーボンクレジットの発行期間はプロジェクトごとに定められた期間内で発行されます。例えば、森林再生プロジェクトでは20~30年間にわたってカーボンクレジットが発行されることが一般的です。政策面では、パリ協定のもとで各国が2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しているため、それに伴いカーボンクレジット市場も長期間にわたって存続する見込みです。特に、日本のJ-クレジットや国際的なVCS認証クレジットは、将来的にも継続的に発行される可能性が高いと考えられます。
カーボンクレジットの価格動向や市場環境は、取り扱われるクレジットの種類や認証制度(例:VCSなど)によって大きく異なります。たとえば、EU-ETS(欧州排出量取引制度)では、1トンあたり100ユーロを超える水準で推移するなど、一定の価格帯での取引が見られます。一方で、ボランタリー市場においては、企業の脱炭素意識の高まりから需要が増加する傾向がある一方で、価格の変動幅も大きいため、十分な理解と情報収集が重要です。あくまでも環境貢献の一環として、長期的な視点で参加いただくことをおすすめしています。
太陽光発電とカーボンクレジットは、それぞれ異なる特徴を持つ環境分野の取り組みです。太陽光発電は、設備の導入によって電力を生み出し、その売電によって中長期的に安定した収入が期待できる仕組みです。ただし、初期コストや設置場所などの条件を考慮する必要があります。一方、カーボンクレジットは、温室効果ガスの削減量を証書化したもので、近年では環境意識の高まりや各国の規制強化により、注目度が高まっています。特に、比較的少額から参加できるケースもあり、柔軟な環境貢献手段として活用されています。ただし、クレジットの市場価格は変動することがあるため、制度や仕組みについて理解したうえで取り組むことが大切です
カーボンクレジットは、不動産の賃貸収入や暗号資産のように、保有しているだけで毎月の収入が発生するものではありません。基本的には、温室効果ガスの削減効果に基づいて発行され、その後、市場の需要動向などを踏まえた活用が行われます。たとえば、企業がカーボン・オフセット(排出量の相殺)を目的としてクレジットを求めるタイミングで適切に対応することで、環境価値を有効に活かすことができます。現在、EU-ETSや日本のJ-クレジット制度など、複数の制度がすでに運用されています。また、当社が提供する予約プログラムでは、一定期間内にクレジットが発行されない場合、所定の条件に基づき70%の買取を行う仕組みも設けており、将来的な計画に対する安心感の向上に努めています。
現在、日本におけるカーボンクレジット関連の取組は、主に企業や団体による活用が中心となっており、個人の方が直接参加しやすい仕組みはまだ発展途上にあります。たとえば、J-クレジット制度なども法人向けの利用を前提とした設計が多く、一般の方が手軽に取り組める選択肢は限定的です。また、カーボンクレジットの価格は市場環境によって変動する側面があり、さらに対応する国内の取引所も限られているため、個人による活用が進みにくい状況があります。一方、海外では制度やインフラの整備が進み、ファンドや専門機関を通じたカーボンクレジット活用が広がっており、日本においても今後、一般の方が参加しやすい環境の整備が期待されています。
カーボンゼログローバルの森林プロジェクトはベトナム北部のホアビン省を中心に展開されており、公式な調査レポートで進捗状況が報告されています。視察などを希望する場合は、カーボンゼログローバルのサポート窓口を通じて事前に問い合わせることで、詳細な情報を確認することが可能です。
カーボンクレジットの取引価格は市場や認証基準によって異なります。例えば、EU排出量取引制度(EU-ETS)では、2025年時点で1トンあたり約100ユーロ(約16,000円)で取引されており、欧州の企業が排出削減義務を果たすために利用しています。一方、日本のJ-クレジット市場では、1トンあたり7,000円~14,000円で推移しており、企業のカーボンオフセット需要に応じて価格が変動しています。国際的なボランタリー市場(VCSなど)では、クレジットの種類やプロジェクトの品質によって価格帯が異なり、1トンあたり約700円~7,000円の範囲で取引されています。価格は需給バランス、政府の政策、企業のカーボンニュートラル戦略などによって変動するため、最新の市場データを確認することが重要です。
カーボンクレジットは発行までに一定の期間を要するため、あらかじめ計画的に準備を進めておくことで、スムーズなプロジェクト推進が可能となります。カーボンゼログローバルでは、すでに森林プロジェクト整備を完了しており、今後の活動も円滑に進められる体制を整えています。
カーボンクレジットの取得は、企業活動の一環として、税務上の一定の効果が期待できるケースもあります。たとえば、購入にかかる費用が外部委託費等として処理されることで、経費としての扱いが可能となる場合があります。これにより、適切な会計処理を通じて、結果的に税務負担の軽減につながる可能性があります。さらに、将来的にカーボンクレジットが企業の環境価値の一部として扱われることで、財務的な側面にも良い影響を与える場合があります。環境への貢献と、長期的な価値創出の両立を目指す手段の一つとしてご検討いただけます。なお、具体的な会計処理や税務対応については、必ず顧問税理士や専門家にご相談のうえ、適切なご判断をお願いいたします。
カーボンクレジットに関する「事前予約」という形で取得の優先権を持つことには、主に3つの意義が考えられます。第一に、「価格変動の影響を抑えやすくなる」点です。今後、環境規制や需要の高まりにより価格が上昇する可能性も想定される中、あらかじめ一定の条件で確保することで、将来の価格変動に備えることができます。第二に、「中長期的な活用価値が見込まれる」点です。カーボンクレジットは、CO₂排出削減に積極的な企業や団体の取り組みに活用されることが多く、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した行動の一環として注目されています。第三に、「計画的な環境対策の推進につながる」点です。クレジットの優先確保により、価格上昇や需給逼迫のリスクを見据えながら、長期的な脱炭素戦略の一部として活用する準備が可能になります。
カーボンゼログローバルでは、「万が一、一定期間内にカーボンクレジットが発行されなかった場合に、予約購入された権利を一定割合で買い取る」旨の契約条件(例:5年以内に発行されなかった場合に予約価格の70%での買取)を導入しています。このような仕組みにより、プロジェクト参加者の皆さまが抱えるリスクの軽減に努めております。
公的な制度はありませんが、個人でもJ-クレジットやボランタリークレジットを購入し、カーボンオフセットに活用することが可能です。
日本国内で森林由来のカーボンクレジットを発行するには、国の制度に基づいて認められた土地の確保が必要です。JCM(Joint Crediting Mechanism)では補助金が活用できる一方で、認証までに時間を要する傾向があります。また、Jクレジット制度は補助金の対象外であり、クレジットの価格水準も比較的低めに設定されているため、事業としての採算性を確保するには工夫が求められます。加えて、土地の取得費用、人件費、認証にかかるコストなどが総じて高く、全体として効率的な運営が難しい側面もあります。このため、日本国内でのクレジット創出を進める場合は、短期的な成果を求めるのではなく、時間をかけた中長期的な取り組みとして捉えることが重要とされています。
ベトナムは現在、「第二の高度経済成長期」を迎えており、2025年にはGDPが日本の1970年代と同じ水準に達すると予測されています。その急成長の理由は、若い労働力の豊富さ、驚異的な経済成長スピード、地理的な優位性、低コストで高い競争力の4点にあります。ベトナムの人口の半分が30歳未満で、労働力がエネルギッシュ。さらに、東南アジアの中心に位置し、低賃金で生産効率も高い。これにより、多くの企業が進出し、世界の工場としての地位を確立しています。今後、ベトナムは成長エンジンとして注目されています。
はい、経済的・環境的に優位です。 日本よりも森林の成長速度が速く、カーボンクレジットの創出コストが低いため、大規模なプロジェクトを実施しやすい特徴があります。
カーボンクレジットが発行されるまでには、植林の成長や森林保全の進捗など、一定の期間が必要となります。そのため、プロジェクト全体は通常、数年単位で段階的に進められます。即座に目に見える結果が得られる取り組みではありませんが、あらかじめプロジェクトにご参加いただくことで、将来的な取り組みの進展を見据えた準備を進めることが可能です。
はい、ご予約に関するお手続きはすべて日本国内で実施されております。また、今後カーボンクレジットの売却が行われた際には、その際の対価も日本円でお受け取りいただける仕組みを整えております。
ベトナムにおける当社の協力企業「インフィニティ・インベンション」は、現地政府より正式に土地使用権の認可を受け、その権利に基づいて森林関連事業を展開しています。土地使用権に関する証書は、当社ホームページの海外事業資料ページにてご確認いただけるよう公開しており、透明性の確保に努めています。なお、ベトナムでは土地の所有権は国家に帰属しており、企業等は政府から使用権を取得することで合法的に土地を活用できる制度となっています。現在、同国では環境保全型の経済政策が進められており、2029年を目処にカーボンクレジット市場の開設も予定されています。これにより、環境対策と経済活動の両立を目指す取り組みが、今後さらに広がっていくことが期待されています。
カーボンクレジットの生成プロセスや森の状態について実際に見学できます。現地で森林や植林地を訪れ、CO₂吸収量を測定する方法や、クレジットがどのように発行されるのかを学べます。また、現地の人々との交流を通じて、地域への貢献も実感できます。見学サポートも充実しており、通訳や移動手配も提供されるため、安心して参加できます。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
山林を購入し、カーボンクレジットの創出を目指すことは可能です。ただし、実際にクレジットを発行するためには、J-クレジット制度や国際的な認証制度(例:VerraのVCS認証など)に基づく森林管理計画の策定や、測定・報告・検証(MRV)体制の構築、さらに追加性の証明が求められます。加えて、プロジェクト開始からクレジットの発行には数年を要し、専門知識とコストが伴います。したがって、山林の購入だけではクレジットが発生するわけではなく、専門家と連携した計画策定が非常に重要です。なお、カーボンゼログローバルを通じて進める場合、山の購入は不要です。カーボンゼログローバルが所有する山林を利用して、カーボンクレジットを発行することができます。
はい、副業的な位置づけで取り組むことも可能です。カーボンクレジットの予約制度は、森林保全や再生可能エネルギーなどの環境プロジェクトを支援するための仕組みであり、当社が提供するプログラムでは、クレジットの創出プロセスが完了した後に、その成果に応じた価値を受け取る形式となっています。日常的な業務のご負担はほとんどなく、本業と並行して環境貢献に参加できる点が特徴です。ただし、カーボンクレジットに関する取り組みは市場や制度の動向に影響を受ける可能性があるため、中長期的な視点で計画的に関与いただくことをおすすめしています。
国際的な排出削減の取り組みにおいては、カーボンクレジットは通常「1トンのCO₂または同等の温室効果ガスの削減・吸収量(tCO₂e)」を1単位として扱われます。こうしたクレジットは、グローバルなボランタリー市場において、米ドル(USD)を基準とした価格で取り扱われることが一般的です。たとえば、VCS(Verified Carbon Standard)認証のクレジットも、国際市場で米ドル建てを基本に取り扱われる傾向があります。なお、為替レートの影響を受ける場面もあるため、各国・地域での導入や活用に際しては、為替変動にも一定の注意が必要とされます。また、パリ協定第6条に基づく国際的なカーボン市場では、「移転可能な削減量(ITMO)」の取扱いが進められており、各国間での排出削減努力の共有・調整を図る仕組みとして検討が進んでいます。
カーボンクレジットの活用には、いくつかの魅力的なポイントがあります。たとえば、①気候変動への対策に貢献できる社会的意義の高さ、②今後の制度整備や企業の環境意識の高まりに伴って需要の増加が期待されている成長分野であること、③株式や不動産などの従来型の資産とは異なる動きをするため、環境価値を活かしたリスク分散の一助となる可能性がある点などです。一方で、注意すべき点もあります。たとえば、①市場の成熟度や価格変動に関する不確実性、②クレジットが創出されるまでに一定の期間がかかること、③プロジェクト内容や認証制度の信頼性・透明性について確認が必要であることなどが挙げられます。このように、環境価値を重視した取り組みである一方で、仕組みや背景をしっかり理解したうえで参加することが大切です。
はい、カーボンクレジットはブロックチェーン技術との親和性が高く、すでにDAO(分散型自律組織)による環境プロジェクトの意思決定や、NFTを活用したカーボンクレジットのデジタル化が一部で進められています。たとえば、VerraやGold Standardといった主要な認証団体も、トークン化されたクレジット(Tokenized Carbon Credit)との連携について、慎重に検討を進めている状況です。今後は、ブロックチェーン上でのカーボンクレジットの管理や追跡、活用方法が多様化し、透明性や利便性の向上につながることが期待されています。
カーボンクレジットに関連する取り組みには、社会的意義のある反面、いくつかの留意点もございます。たとえば、①クレジットの価格は市場の需給バランスによって変動する可能性があること、②自然環境や技術的要因などにより、プロジェクトが計画どおりに進まず、クレジットの発行に時間を要する場合があること、③制度改正や国際的なルールの変更によって市場環境が変わる可能性があることなどが挙げられます。こうした点を踏まえ、当社では一定の安心材料として、「万が一クレジットが所定期間内に発行されなかった場合には、予約権の70%を目安に当社が買い取る」という独自の仕組みを設けています。これは、プロジェクトの進捗に対する責任を共有しながら、参加者の皆さまの不安を軽減することを目的としたものであり、元本の保証を意味するものではありませんが、環境貢献とリスク抑制の両立を目指した制度となっています。
一見似た点はありますが、本質的には異なります。カーボンクレジットは、実際に温室効果ガスを削減・吸収した実績に基づいて発行される「環境価値」の証明であり、実体のない暗号資産(仮想通貨)とは異なります。ただし、近年はカーボンクレジットをブロックチェーンでトークン化して取引する動きもあり、「仮想通貨化されたカーボンクレジット」の開発も進んでいます。したがって、技術的には重なる部分がありつつも、原理的には違う仕組みです。
カーボンクレジットの予約手続きが完了し、クレジットが発行・割当された際には、原則としてお申込者に対し当該クレジットの利用に関する優先的な権利が付与される形となります。ただし、具体的な取り扱いや登録方法(例:管理台帳への記録、償却に関する権限の有無など)は、各プロジェクトや契約スキームにより異なります。そのため、事前に契約書や資料の内容をご確認いただくことを推奨しております。カーボンゼログローバルでは、予約手続きからクレジットの割当までを一貫してご案内し、関係書類の整備や管理体制の透明化にも努めております。
一部正しい側面もありますが、それがすべてではありません。たとえば、森林保全や植林によって二酸化炭素を吸収する取り組み(REDD+や植林プロジェクトなど)は、カーボンクレジットの主な分野のひとつであり、森林と深い関わりがあります。その一方で、クレジットの対象となる活動は幅広く、再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の向上、農業・土壌管理など、多様な温室効果ガス削減の取り組みが含まれます。したがって、「カーボンクレジット=森林」というイメージは一部には当てはまりますが、クレジットが生まれる背景にはさまざまな環境改善のプロジェクトがあることをご理解いただければと思います。
クレジットの発行時期は、プロジェクトの開始時期や植林・生育状況、また認証機関(例:Verraなど)による検証スケジュールにより変動します。そのため、クレジット発行の見込み時期は、契約締結時にお客様ごとに明記され、個別にご案内させていただきます。通常は契約後3~5年を目安に初回クレジットが創出される想定です。詳細なスケジュールは、プロジェクトごとの進捗に基づき都度ご連絡いたします。
当社も本プロジェクトに主体的に関わっており、契約者の皆さまと同様に、創出されたカーボンクレジットに関わる立場にあります。これは、単なる事業運営ではなく、私たち自身が環境貢献の一環として責任を果たしていく姿勢の表れです。私たちは、この取り組みを通じて、温室効果ガス削減や持続可能な社会の実現に直接的に寄与していきたいと考えております。そのため、関わる皆さまとリスクを共にしながら歩みを進めることを大切にしています。お客様と共に信頼を築き、環境のために未来へつながる道を一緒に切り開く、真のパートナーであり続けることを目指しています。
国内外では、カーボンクレジットに関連する取り組みを進める企業が年々増加しています。主な事例としては、以下のような動きが見られます。
- 丸紅株式会社や三菱商事株式会社などの大手商社:海外の再生可能エネルギー事業や森林保全プロジェクトに参画し、カーボンクレジットの創出に取り組んでいます。
- リコー株式会社やトヨタ自動車株式会社などの製造業企業:自社での温室効果ガス削減を進めると同時に、余剰となったクレジットの活用を検討しています。
- ブルーカーボン関連のスタートアップ:マングローブや海藻など海洋資源を活用し、新たなクレジット創出の可能性を追求しています。
なお、当社ではベトナムの森林保全活動を通じて創出されるカーボンクレジットに関し、将来的な取得に関する優先的な参加枠をご案内する取り組みを行っております。個人の方々にもご関心をお持ちいただけるような仕組みを提供している点で、国内では比較的先進的な事例と考えています。
- 丸紅株式会社や三菱商事株式会社などの大手商社:海外の再生可能エネルギー事業や森林保全プロジェクトに参画し、カーボンクレジットの創出に取り組んでいます。
- リコー株式会社やトヨタ自動車株式会社などの製造業企業:自社での温室効果ガス削減を進めると同時に、余剰となったクレジットの活用を検討しています。
- ブルーカーボン関連のスタートアップ:マングローブや海藻など海洋資源を活用し、新たなクレジット創出の可能性を追求しています。
なお、当社ではベトナムの森林保全活動を通じて創出されるカーボンクレジットに関し、将来的な取得に関する優先的な参加枠をご案内する取り組みを行っております。個人の方々にもご関心をお持ちいただけるような仕組みを提供している点で、国内では比較的先進的な事例と考えています。
ベトナムでは、土地の私有制度が存在せず、土地は基本的に国有とされ、個人・法人は使用権(Land Use Right)を保有する仕組みとなっています。これは制度上の特性であり、不安材料とは一概には言えませんが、カーボンクレジット創出上いくつかのリスクが考えられます。
- 土地使用権証書の有効性や取得状況の確認
- 地元行政との合意形成の状況
- プロジェクト実施区域の長期管理体制
当社では、現地法人であるInfinity Invention社と連携し、適切な土地使用権の取得および行政の許認可手続きを済ませた上でプロジェクトを進行しています。また、必要に応じて土地使用権証書等の閲覧もご案内可能ですので、ご安心ください。
- 土地使用権証書の有効性や取得状況の確認
- 地元行政との合意形成の状況
- プロジェクト実施区域の長期管理体制
当社では、現地法人であるInfinity Invention社と連携し、適切な土地使用権の取得および行政の許認可手続きを済ませた上でプロジェクトを進行しています。また、必要に応じて土地使用権証書等の閲覧もご案内可能ですので、ご安心ください。
2025年4月時点において、当社カーボンゼログローバルは、個人の方にもご参加いただける「カーボンクレジット予約購入制度」を独自に構築・公開しております。国内では、森林整備や再生可能エネルギーの導入を通じてカーボンクレジットを取得する取り組みは複数存在しますが、小口単位での予約購入という形で一般の方にアプローチし、さらに将来のクレジット創出に向けた一定の買取条件を設けている事例は、比較的珍しいと認識しています。今後も、環境貢献と参加しやすさを両立した枠組みづくりに努めてまいります。
カーボンクレジットの信頼性を確保するうえで、第三者の認証機関(例:Verra〈VCS〉、Gold Standardなど)による審査は非常に重要です。以下のような特長があります。
- 測定・報告・検証(MRV)を厳格な基準で行うことで、排出削減量の客観性を担保できる
- 国際市場での取引が可能となり、クレジットの流通性が高まる
- ESGの観点から評価されやすく、企業による活用ニーズが高まる
当社においても、ベトナムでのプロジェクトにおいてVerraのVCS認証取得を予定し、準備を進めております。
- 測定・報告・検証(MRV)を厳格な基準で行うことで、排出削減量の客観性を担保できる
- 国際市場での取引が可能となり、クレジットの流通性が高まる
- ESGの観点から評価されやすく、企業による活用ニーズが高まる
当社においても、ベトナムでのプロジェクトにおいてVerraのVCS認証取得を予定し、準備を進めております。
日本国内でカーボンクレジットを認証する制度として代表的なものは「J-クレジット制度」です。これは環境省・経済産業省・農林水産省の3省が共同で運営しており、民間企業や自治体が省エネや再エネ、森林整備等によって削減・吸収したCO₂をクレジット化するための公的制度です。 J-クレジット制度では、登録された検証機関(第三者機関)が申請内容を審査・確認し、正式にクレジットが発行されます。2024年時点で10社以上の登録検証機関が活動しています。これに加えて、国際的にはVerra(VCS)やGold Standard、Plan Vivoなど複数の認証団体があり、プロジェクトのタイプや販売先に応じて使い分けられています。
ご認識のとおり、カーボンクレジットはその創出源によって、主に「再生可能エネルギー由来(例:太陽光・風力)」「森林由来(例:植林・森林保全)」「メタン削減型」「農業・土壌管理型」などに分類されます。それぞれに特徴があり、市場で重視されるポイントや需要動向には違いがあります。
たとえば、再エネ由来のクレジットは、比較的短期間で大量に創出できる利点があり、大規模な需要につながりやすい一方で、プロジェクトによっては「追加性(その取り組みによって実際に削減が実現したのか)」について議論になることもあります。
一方、森林由来のクレジットは、成果が現れるまで時間を要する反面、「CO₂吸収」「生物多様性保全」「地域との共生」などの共益(コベネフィット)が評価されやすく、近年では多くの企業から注目を集めています。
最終的に市場で重要視されるのは「クレジットの質」です。その質を決定づけるのは、認証機関による厳格な検証を経たプロジェクトであるかどうかです。弊社では、グループ全体で環境分野に長年取り組んできた実績を活かし、第三者認証機関(例:Verraなど国際基準、または日本のJ-クレジット制度)との連携を重視しています。
国内においても、J-クレジット認証を行う検証機関は現在10社程度に限られており、信頼性の高いスキームであるかどうかは、こうした機関と連携しているプロジェクトであるかどうかが大きな判断基準のひとつとなります。
たとえば、再エネ由来のクレジットは、比較的短期間で大量に創出できる利点があり、大規模な需要につながりやすい一方で、プロジェクトによっては「追加性(その取り組みによって実際に削減が実現したのか)」について議論になることもあります。
一方、森林由来のクレジットは、成果が現れるまで時間を要する反面、「CO₂吸収」「生物多様性保全」「地域との共生」などの共益(コベネフィット)が評価されやすく、近年では多くの企業から注目を集めています。
最終的に市場で重要視されるのは「クレジットの質」です。その質を決定づけるのは、認証機関による厳格な検証を経たプロジェクトであるかどうかです。弊社では、グループ全体で環境分野に長年取り組んできた実績を活かし、第三者認証機関(例:Verraなど国際基準、または日本のJ-クレジット制度)との連携を重視しています。
国内においても、J-クレジット認証を行う検証機関は現在10社程度に限られており、信頼性の高いスキームであるかどうかは、こうした機関と連携しているプロジェクトであるかどうかが大きな判断基準のひとつとなります。
カーボンクレジットを取得する方法にはさまざまな選択肢があり、たとえば取引所(例:JPX)を通じた購入と、弊社のようなプロジェクト型スキームを通じた予約型の取得とでは、その目的やタイミング、想定される活用スタイルが大きく異なります。そのため、比較検討の際には「何を目的としてカーボンクレジットを取得したいのか」を明確にすることが大切です。取引所での取得は、すでに発行・認証されたクレジットをその場で購入する、いわば「スポット取引」の形式です。価格は市場の需給バランスによって決まり、2025年現在、J-クレジットは1トンあたり約6,400円前後が一般的な水準とされています。このような形式は、企業による自社排出のオフセットや、短期的なESG対応策として利用されることが多い傾向にあります。
一方、弊社がご案内するスキームでは、今後創出される予定のカーボンクレジットに関して、一定の優先取得枠をご希望者にご案内する「予約型」の形式を採用しています。この方式には、たとえば以下のような特徴があります:
・将来的な価格変動の影響を受けにくい水準であらかじめ取得の準備ができる
・プロジェクトの初期段階から携わる形となるため、創出過程をより深く理解できる
・長期的な環境価値への貢献を意識した取り組みが可能となる
さらに、当社スキームでは、万が一クレジットが創出されなかった場合に備えて、一定の条件のもとで「70%の金額買取」に対応する仕組みも設けており、リスク軽減にも配慮しています。 ただし、この予約型の取得には、実際にクレジットが創出されるまで一定の期間を要するため、資金が長期にわたりプロジェクトに関与することになる点や、市場価格の変動によって想定とは異なる結果となる可能性もある点にはご留意ください。 短期的な調達ニーズやオフセットを重視される場合は取引所での取得が適している一方で、プロジェクトへの関与や長期的な環境価値の創出を重視される方には予約型スキームも一つの選択肢となり得ます。ご自身の目的に応じて、適切な方法をお選びいただければ幸いです。
一方、弊社がご案内するスキームでは、今後創出される予定のカーボンクレジットに関して、一定の優先取得枠をご希望者にご案内する「予約型」の形式を採用しています。この方式には、たとえば以下のような特徴があります:
・将来的な価格変動の影響を受けにくい水準であらかじめ取得の準備ができる
・プロジェクトの初期段階から携わる形となるため、創出過程をより深く理解できる
・長期的な環境価値への貢献を意識した取り組みが可能となる
さらに、当社スキームでは、万が一クレジットが創出されなかった場合に備えて、一定の条件のもとで「70%の金額買取」に対応する仕組みも設けており、リスク軽減にも配慮しています。 ただし、この予約型の取得には、実際にクレジットが創出されるまで一定の期間を要するため、資金が長期にわたりプロジェクトに関与することになる点や、市場価格の変動によって想定とは異なる結果となる可能性もある点にはご留意ください。 短期的な調達ニーズやオフセットを重視される場合は取引所での取得が適している一方で、プロジェクトへの関与や長期的な環境価値の創出を重視される方には予約型スキームも一つの選択肢となり得ます。ご自身の目的に応じて、適切な方法をお選びいただければ幸いです。
カーボンクレジット市場は現在も成長段階にあり、プロジェクトの内容や市場の動向によって価値の変動幅が見られます。当社がご案内しているカーボンクレジット予約制度においては、仮にプロジェクトが順調に進行した場合、将来的に取得されるクレジットの価格変動などをもとに、シミュレーション上で10〜30%程度の価格上昇余地を想定するケースもあります。これは、市場におけるクレジット供給量の制限や、需要拡大の影響によるものと考えられています。
一方、現在すでに取引所(JPXなど)で流通しているJ-クレジットを購入する場合、すでに確定した価格帯での取引となるため、今後の価格上昇による変動幅は限定的といえるかもしれません。また、取引所においては「事前予約」や「一定の付加条件付きでの取得制度」などは基本的に提供されておらず、利用方法は比較的シンプルなものに限られています。
なお、J-クレジットの市場価格は、過去10年で1トンあたりおよそ500円から6,400円まで上昇した実績があり、長期的に見れば約11倍の価格変動が起こった例もあります。今後も企業のカーボンオフセット需要の高まりや政策動向によって、さらなる価格の上昇が期待されるという見方もあります。
また、流通市場以外の相対取引においては、1トンあたり50,000円で販売されたケースがあるとも言われており、希少性や需要の高さによって価格に幅が生じるのが特徴です。
一方、現在すでに取引所(JPXなど)で流通しているJ-クレジットを購入する場合、すでに確定した価格帯での取引となるため、今後の価格上昇による変動幅は限定的といえるかもしれません。また、取引所においては「事前予約」や「一定の付加条件付きでの取得制度」などは基本的に提供されておらず、利用方法は比較的シンプルなものに限られています。
なお、J-クレジットの市場価格は、過去10年で1トンあたりおよそ500円から6,400円まで上昇した実績があり、長期的に見れば約11倍の価格変動が起こった例もあります。今後も企業のカーボンオフセット需要の高まりや政策動向によって、さらなる価格の上昇が期待されるという見方もあります。
また、流通市場以外の相対取引においては、1トンあたり50,000円で販売されたケースがあるとも言われており、希少性や需要の高さによって価格に幅が生じるのが特徴です。
いいえ、お客様ご自身でカーボンクレジットを個別に売買いただく必要はございません。当社では、プロジェクトで創出されたクレジットを一括して管理し、あらかじめ定めた手順に従って販売・活用を進める体制を整えております。そのため、お客様には煩雑な手続きや価格調整などをご負担いただくことなく、ご関心に応じてスムーズにご参加いただけます。環境分野に初めて関わる方にも安心していただけるよう、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
はい、一定の額が発生した場合には、原則として確定申告が必要となることがあります。特に、源泉徴収が行われていないケースや、他の項目と合算した結果として税金の納付が必要となる可能性があります。内容や額により、税務上の区分が異なる場合もありますので、詳細についてはその年の状況に応じて、税理士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。なお、この取り組みは単なる金銭的なやり取りを目的とするものではなく、地球温暖化対策や森林保全など、環境貢献の一環として進められているものです。関わる皆さまには、この社会的な意義をご理解いただいたうえでご参加いただければ幸いです。
いいえ、カーボンクレジットは国際的に活用されており、日本企業に限らず、海外の企業や機関も積極的に参加しています。特に欧州や北米では、炭素排出に関する規制が厳格であることから、カーボンクレジットへの需要が非常に高まっています。当社としても、国内外の多様な関係者と連携できる体制を整えており、環境貢献の取り組みをより広く推進できるよう努めております。カーボンクレジットの活用は、単なる制度上の対応ではなく、地球温暖化防止や持続可能な社会の実現に直結する重要な取り組みです。私たちは、その一環を担う立場として、信頼性と透明性を重視しながら、世界中の仲間と共に歩んでまいります。
カーボンクレジット創出量シミュレーターで示される5%という上昇率は、あくまで「将来的な市場動向を踏まえた予測値」であり、確定したものではありません。根拠としては、過去のJ-クレジットやVCSクレジットの取引価格推移、世界的な排出規制の強化傾向、炭素税や排出量取引制度の拡大、そしてESGに関する取り組みの広がりなどを考慮し、保守的に設定しています。過去10年間でJ-クレジットは1トンあたり500円から6,400円へと約11倍に上昇しており、今後も需要拡大に伴う価格上昇が見込まれます。ただし、市場価格である以上、将来的には上下の変動が起こり得る点にもご留意いただく必要があります。
本取り組みは、あらかじめ決まった結果が確定しているものではなく、カーボンクレジットの売買予約権をご利用いただく形となっております。そのため、ご参加いただいた方には、ご購入いただいた予約権の数量に応じて反映される仕組みを採用しています。また、弊社では、一定期間内にクレジットの創出が確認できなかった場合に備え、「5年以内に創出が確認できなかった場合には、70%での買い取りを行う条項」を契約に明記しております。これは、環境貢献の一環として取り組んでいただく皆さまに、より安心して関わっていただけるよう、不確実性を抑えるための仕組みです。私たちは、カーボンクレジットを通じて温室効果ガス削減や森林保全といった地球環境への直接的な貢献を進めており、この取り組みに参加いただくことそのものが、未来に残す責任ある行動であると考えています。
どうぞご安心ください。カーボンクレジットの管理や取扱いといった複雑な業務は、すべて弊社が責任を持って対応しております。ご参加いただく皆さまが市場のタイミングを判断したり、直接売買の手続きを行っていただく必要は一切ございません。弊社では、環境貢献の取り組みとしてクレジットを最大限に活用できる時期を見極め、適切な方法で取り扱いを進めております。また、プロジェクトの進捗や関連情報については、マイページ等を通じて随時ご確認いただける体制を整えており、初めて関わる方にも安心してご参加いただけるよう、分かりやすいご案内を心がけております。この仕組みは、単なる取引のためではなく、地球温暖化防止や森林保全といった環境貢献の一環として存在しています。私たちは、この取り組みに関わるすべての方が「未来の環境を共につくる仲間」となれるよう、誠実にサポートを続けてまいります。
はい、原則としてカーボンクレジットの予約権は相続や第三者への譲渡が可能です。ただし、実際の譲渡手続きに際しては、当社所定の名義変更届出書や相続関係書類(戸籍謄本や遺産分割協議書等)のご提出が必要となります。また、予約権の契約形態によっては、譲渡・相続時に一定の事務手数料や同意確認手続きが発生する場合があります。
万が一、ご購入者様がご逝去された場合には、法定相続人の方にご連絡いただき、当社が所定の手続きに基づき権利の移転処理を行います。マイページの閲覧権限や受取口座の変更なども含め、できる限り円滑に対応できる体制を整えております。相続時の税務上の取扱い(評価額や税区分など)については、専門の税理士へのご相談をおすすめしております。
現在、ベトナムで進めている森林プロジェクトには、複数の法人企業様から前向きなご関心をいただいており、協議や調整が進んでおります。ただし、2025年5月時点では、契約上の守秘義務により、公開可能な企業名は一部に限られます。詳細については、個別の面談やご相談の場にて、適切にご案内いたします。当社の活動は、ご参加いただいた費用の一部をプロジェクトの企画・管理・推進に充てるとともに、創出されたカーボンクレジットの一部を自らも活用することで成り立っています。これにより、当社自身もプロジェクトの進展と歩調を合わせながら責任を持って関与し、参加者の皆さまと同じ視点で環境貢献の意義を共有しております。私たちは「共に取り組み、共に歩む」という姿勢を大切にしながら、地球温暖化防止や森林保全といった環境課題の解決に真摯に向き合っています。事業の継続は単なる活動の維持ではなく、次世代により良い地球環境を引き継ぐための責任であると考えております。
はい、VCS(Verified Carbon Standard)の取得は弊社として最優先事項のひとつであり、現在、ベトナム政府および国際認証機関であるVerraとの連携のもと、プロジェクト登録の準備を進めております。2025年後半にかけて、必要な現地調査・ベースライン設定・モニタリング体制の構築を進めており、2026年内のVCSプロジェクト登録および初回クレジット創出を目指しています。
VCS認証は、国際的に最も広く利用されているカーボンクレジット認証制度であり、取得にあたっては厳格な測定・報告・検証(MRV)が求められます。当社では、専門コンサルタントおよび現地林業パートナーと連携し、認証取得の要件を段階的にクリアしてまいります。正式な登録時期や承認プロセスが進展しましたら、順次契約者の皆さまにご報告いたします。
カーボンクレジットは、地球温暖化防止のための取り組みを証明する仕組みであり、環境貢献の一環として国際的に活用されています。その多くは米ドル建てでやり取りされるため、日本円に換算する際には為替の変動が反映される場合があります。ただし、私たちが最も重視しているのは、為替の変動そのものではなく、この仕組みを通じて温室効果ガス削減を進め、持続可能な社会づくりに貢献することです。為替の影響はあくまで国際的な活動を進める上での事務的な側面に過ぎません。弊社では、参加いただく皆さまが安心して取り組みに関わっていただけるよう、環境プロジェクトの進捗や関連情報を透明性を持ってご案内し、共に未来に向けた歩みを進めてまいります。
恐れ入りますが、カーボンゼログローバル株式会社は現在、東京証券取引所には上場しておらず、企業コードも付与されておりません。当社は未上場の独立系企業として、森林を活用したカーボンクレジット創出に特化した取り組みを行っております。現在は、関心をお寄せくださる皆さまと丁寧な対話を重ねながら、持続可能なプロジェクト開発に取り組んでおります。将来的には、事業の成長段階に応じて、外部からの信頼性をより一層高める施策も検討してまいります。
契約者様がご逝去された場合には、その契約上の権利(例:予約購入権など)は、法定相続人の方へ適切に承継されます。相続手続きにあたっては、戸籍謄本、遺産分割協議書、名義変更届出書など、所定の書類をご提出いただくことで、名義変更や関連する手続きを進めることが可能です。当社では、万が一の事態に備え、円滑に相続が行えるよう内部体制を整備しており、ご希望に応じて個別のサポートも行っております。また、相続時の税務に関する取り扱いについては、税理士など専門家へご相談いただくことを推奨いたします。私たちは、この取り組みを単なる契約事務にとどめるのではなく、環境貢献を社会全体で持続させるための大切な仕組みと捉えています。契約者様が亡くなられた後も、次の世代へと継承されることで、地球環境の保全に向けた歩みが途絶えることなく続いていくことを目指しています。
ご懸念はもっともであり、大変重要なご質問と受け止めております。弊社のプロジェクトでは、現地法人(提携会社)の名義で森林の使用権および開発権を正式に取得し、関係法令や契約に則った分別管理のもとでプロジェクトを進行しております。仮に弊社に万が一の事態が生じた場合でも、現地法人や関係機関によってプロジェクトの継続が可能となるよう、構造面から分散的な体制を整えております。これにより、プロジェクトの信頼性と持続性を担保する体制を構築しています。また、弊社では一定期間内にカーボンクレジットが創出されなかった場合の「70%買取の対応(例:5年以内に創出されない場合など)」といった、参加者の皆さまの不安軽減につながる仕組みを契約内に設けております。さらに、今後はご要望や状況に応じて、第三者機関や信託等の導入を含むスキームの検討も視野に入れ、より一層の信頼確保に努めてまいります。私たちは、プロジェクトの透明性と健全性を何よりも重視し、参加される皆さまの安心を守るべく、法務・契約・ガバナンスの体制強化に引き続き注力してまいります。
政府規制とは無関係に、企業や個人が自主的に利用するカーボンクレジットです。 VCSやゴールドスタンダードが代表的な認証基準です。
京都議定書の枠組みで、先進国が途上国の排出削減プロジェクトを実施し、得られた削減量をクレジット化できる制度です。
Verraが運営するカーボンクレジット認証制度です。 世界で最も普及しているボランタリークレジットの基準であり、森林保全・再生可能エネルギーなどのプロジェクトに適用されます。
カーボンクレジットの国際認証を行う非営利団体です。 VCS認証の管理主体であり、気候変動対策の信頼性向上に貢献しています。
二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism)。 日本と協定を結んだ国(例:ベトナム)での温室効果ガス削減をクレジット化し、相互に活用できる制度です。
成長が早く、CO₂吸収能力が高い樹木です。 熱帯地域で植林され、カーボンクレジットの創出に適しています。
基本的に不可です。 雑草は長期的な炭素固定が難しく、認証基準を満たしません。
2029年に正式に開設予定です。 2025年現在、政府が市場整備を進めています。
一般的な企業がいずれか一方の市場に特化するのとは異なり、当社では「デュアル認証戦略」を採用しています。具体的には、政府や公的機関が利用するコンプライアンス市場向けのJCM認証と、企業が自主的な取り組みとして利用するボランタリー市場向けのVCS認証の双方を取得する方針です。これにより、どちらかの市場で需要や価格の変動があった場合でも、柔軟に対応できる選択肢を確保しています。二つの市場で販売機会を持つことで、プロジェクトの継続性や安定的な運営体制の確保につながると考えています。
当社では、万が一カーボンクレジットの創出が計画どおりに進まなかった場合にも、関わる皆さまに安心していただけるよう「5年以内に創出が確認できなかった場合には、70%で買い取りを行う条項」を契約に盛り込んでおります。これは、不確実性を低減し、取り組みを長期的に持続可能なものとするための仕組みです。その際には、プロジェクト用地を森林経営に転換し、伐採・加工した木材を有効活用することで、環境への貢献を継続してまいります。木材は世界的に需要が高く、特にベトナムはインドや中国といった大規模需要国に近接しているため、環境資源としての活用にも適した地域性を備えています。このように、当社は「いかなる状況でも環境貢献を途絶えさせない」という姿勢を大切にしています。クレジット創出だけでなく、森林資源の循環利用を通じて社会全体の脱炭素化を支え、持続的な環境保全の仕組みを築いていくことが、私たちの使命です。
カーボンクレジットにご興味のある方は、ぜひ当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。専任の脱炭素アドバイザーが、初心者の方にもわかりやすく丁寧にご説明し、目的に合った最適な方法をご提案いたします。現在、ベトナムではCO₂削減を目的とした植林によるカーボンクレジット創出プロジェクトが進行しており、実際にクレジットが発行され、企業や自治体によって活用されています。この取り組みは、環境保全と経済的価値の両立を実現するものです。私たちと一緒に、地球の未来を守る新しい一歩を踏み出しましょう。