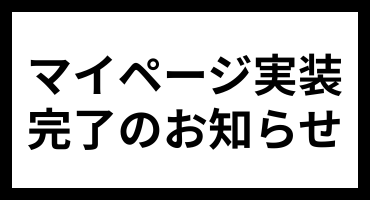「マウントを取る癖」を手放すことが、信頼を築く第一歩
最近、SNSでも職場でも、「マウントを取る人」にうんざりしているという声をよく耳にします。
相手より優位に立とうとする言葉、何気ない比較や自慢。
誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。
しかし、そんな行為が実は自分の価値を下げ、信頼を失う一番の原因になっているとしたら──どう感じますか。
■ 「マウント社会」が生まれた背景
今の時代、私たちは常に「比較」の中に生きています。
SNSでは、他人の成功や豊かさが絶えず流れてきます。
職場では成果や地位が評価の軸となり、「誰が優れているか」という視点が自然に植え付けられている。
その結果、知らず知らずのうちに私たちは“自分の価値を他人との相対で測る”ようになってしまいました。
そして、自信が揺らいだときに現れるのが──「マウントを取る」という防衛反応です。
しかし、マウントとは自己防衛の裏返しであり、決して強さの証ではありません。
むしろ、「自分を大きく見せなければ、認めてもらえない」という心の不安の表れなのです。
■ 信頼は「上下」ではなく「共感」から生まれる
私はこれまで、経営やプロジェクトの現場で多くの人と関わってきました。
その中で痛感しているのは、人は「すごい人」に惹かれるのではなく、「誠実な人」に信頼を寄せるということです。
どれほど知識や実績があっても、相手を見下すような態度を取った瞬間に、信頼は静かに離れていきます。
一方で、相手の立場を理解し、敬意をもって接する人は、時間が経つほどに信頼を積み重ねていきます。
結局、仕事とは「いかに信頼され、好かれるか」というゲームです。
マウントを取るという行為は、その土俵から自ら降りてしまうようなもの。
本当に強い人は、相手を下げることではなく、相手を認めることで自分を高める人なのです。
■ 私が学んだ「信頼される人」の共通点
過去に私が出会った尊敬すべき経営者やリーダーたちは、例外なく「謙虚さ」を持っていました。
彼らは自分の実績を誇るよりも、相手の努力や価値を認めることを何より大切にしていました。
印象的だったのは、ある経営者の言葉です。
「信頼は、“自分の話をすること”ではなく、“相手の話を聴くこと”から始まる」
その姿勢は、人を自然と惹きつけ、周囲が協力したくなる雰囲気をつくっていました。
誠実さとは、声高に主張するものではなく、態度で伝わる静かな力なのだと感じます。
■ これからの時代に必要なのは「競争」ではなく「共創」
これからの社会は、「勝つか負けるか」ではなく、「共に創るかどうか」の時代へと移行していきます。
地球環境も、経済も、個人の生き方も、すべてがつながりの中で成り立っています。
だからこそ、誰かの上に立つのではなく、誰かと共に歩むリーダーシップが求められています。
その第一歩は、他人と比べることをやめ、「自分の軸」を持つこと。
そして、どんな場面でも謙虚さと敬意を忘れないことです。
マウントを取る行為は、一瞬の優越感をくれるかもしれません。
けれど、その代償として失うのは、「信頼」という何よりも大切な資産です。
誠実な姿勢は、時間がかかるように見えて、実は最も早く成果へとつながる道です。
人に敬意を払い、相手を認めること。
それこそが、これからの時代を生き抜く“本当の強さ”ではないでしょうか。
あなたは今日、どんな言葉で誰かを励ましますか?
小さな一言が、誰かの心を温め、信頼を育てる最初の一歩になるかもしれません。