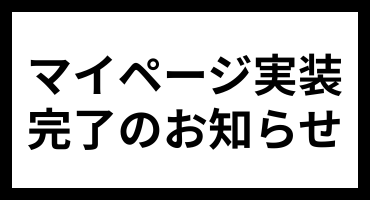五島列島から始まる「循環型未来」──地域と自然資本が紡ぐ、新しい日本の挑戦

最近、私たちは「環境」と「地域経済」の両立という、長年取り残されてきた課題と真剣に向き合わざるを得ない時代に入りました。
地球規模での気候変動、人口減少に直面する地方、そして持続可能な暮らしへの模索。
こうした変化の中で、皆さんはどのように未来を描いていらっしゃるでしょうか。
私自身、この数年間で森林事業やカーボンクレジット事業、地域創生の現場に深く関わる中で、「自然資本を軸にした地域循環型社会こそ、これからの日本の希望である」と強く確信するようになりました。
その象徴ともいえる取り組みが、長崎県・五島市で始まった「つなクレ」事業です。
■ 五島で始まった、新しい挑戦の本質
今回、一般社団法人みつめる旅を中心とした民間4者(みつめる旅、アイフォレスト、杣林、ヤマハ発動機)と五島市は、吸収系ボランタリーカーボンクレジット(JVC)創出と地域循環ビジネス構築に向けた協定を締結しました。
対象となるのは、五島市・久賀島にある約815haの未施業市有林。
ここで「森林保全」「人材育成」「地域コミュニティ形成」を同時に実現しながら、国際基準に沿ったカーボンクレジットをつくるという、国内でも先進的な取り組みです。
特に注目すべきは、
✔ 九州大学都市研究センター
✔ NCCC(ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム)
によるCO₂吸収量・生物多様性の科学的評価に基づく国際基準での認証が予定されている点です。
これは、単なる植林でも、補助金頼りの地域事業でもありません。
日本が世界に誇れる「科学と地域の連携」が形になろうとしている瞬間なのです。
■ 背景にある、日本社会が抱える構造的な課題
このプロジェクトが重要である理由は、表面的な環境事業という枠にはありません。
私たちが直面しているのは、
・森林事業者の不足
・地方の人口減少
・自然資本の衰退
・地域経済の停滞
・脱炭素化の国際競争
こうした複数の課題が複雑に絡みあう「構造問題」です。
森林は育つのに50年以上かかります。しかし、担い手はどんどん減り、手入れされない森が全国に広がっている。
一方で、日本企業は脱炭素に向けて“良質なクレジット”を強く求め始めていますが、国内供給はまだ足りていません。
つまり、日本には
「守るべき森があるのに、守る人がいない」
「クレジットの需要はあるのに、供給が追いつかない」
という深刻なギャップが存在しています。
五島での取り組みは、このギャップを埋める突破口になり得るのです。
■ 私自身の信念──自然資本と地域をつなぐ、新しい価値創造
私は、森林事業に携わる中で何度も「森を守ることは、未来を守ることだ」と痛感してきました。しかし同時に、森は「善意」だけでは守れない。
経済性、科学性、そして地域の誇りのすべてが揃って初めて継続できるのです。
五島の「つなクレ」は、この三つが見事に組み合わさった取り組みです。
・地域の人が関わり、誇りを取り戻す
・科学的に裏付けられたクレジットが世界で評価される
・森が持続可能な“経済価値”を生む
この循環が美しく回り始めるとき、森は「コスト」ではなく「資産」になります。
そして私は、
日本の地方こそが、世界の脱炭素を牽引する時代をつくれる
と本気で信じています。
■ では、私たちは何をすべきか
私は今、
・森林事業者の育成
・カーボンクレジット事業の透明化
・地域を巻き込んだ新しい経済モデルづくり
に力を入れています。
この「五島モデル」は、全国に広げていくべきプロトタイプです。
そして、この記事を読んでくださっている皆さんにも、ぜひ次の問いを共有したいと思います。
──私たちは、地域と自然資本の未来にどう関わっていくのか?
答えは一つではありません。
しかし、対話を始めることが第一歩です。
■ 最後に
五島市で始まった「つなクレ」は、単なる地域プロジェクトではありません。
日本が次の時代に向けて選ぶべき、新しい道の象徴だと私は考えています。
森を守り、人を育て、地域を再生する。
その循環の中心に「自然資本」がある社会は、決して夢物語ではありません。
私は、こうした未来を皆さんと共に創っていけることを心から願っています。