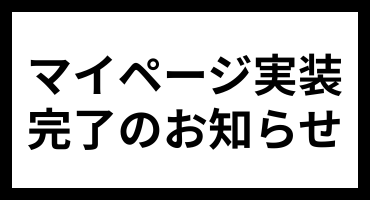【ビジネスとリアル】理想だけでは動かない現実と、そこから見える未来
最近、カーボンクレジットという言葉を耳にする機会が増えてきました。
気候変動への関心が高まる中で、「環境と経済の両立を目指す新しい仕組み」として期待されています。しかし同時に、「それは本当に機能しているのか」「理想論に過ぎないのではないか」といった疑問も多くの方が抱いているのではないでしょうか。
カーボンクレジットは理想だけでは回らない
私自身、この分野に身を置いて強く実感しているのは、「カーボンクレジットは美しい理念だけでは回らない」という事実です。
市場における透明性や信頼性の確立、現場での実装力、そして何よりも“泥臭い調整”が不可欠です。理想だけを語っていても、現実は一歩も前に進みません。
現実は地味で泥臭い。でもそれが“強さ”になる
ベトナムの森林プロジェクトに携わっていると、予想もしなかった課題に次々と直面します。書類一枚に何週間もかかることもあれば、文化や習慣の違いで一から説明をやり直すこともあります。
一見すると非効率に思えるこうした過程こそが、プロジェクトの「本当の強さ」を育んでいるのだと感じます。華やかな成果の裏には、地味で積み重ね型の努力が必ずあるのです。
「仕組みがないなら、つくればいい」と思えた瞬間
ある時、現地で必要とされている制度や枠組みがまだ存在していない場面に直面しました。最初は戸惑いもありましたが、その時「仕組みがないなら、つくればいい」と心から思えました。ゼロから制度を構築するのは骨の折れる仕事です。しかし、その積み重ねが未来のスタンダードを形づくるのだと確信しています。
日本とベトナム。現地で感じた“価値観のズレ”
また、日本とベトナムの間には、環境問題に対する優先順位や価値観の違いもあります。日本では「地球の未来のために」という抽象的な表現が響く一方、ベトナムでは「地域の生活改善」や「直接的な経済的利益」が重視されます。
その違いをどう橋渡しするかが、グローバルに取り組む上での大きなテーマだと感じています。
ゼロから1をつくるということは、9回失敗するということ
ゼロから新しい仕組みを立ち上げるということは、9回失敗してやっと1回成功することに等しいものです。失敗の連続を前提にしなければ、挑戦などできません。
私自身、数え切れないほどの壁にぶつかってきましたが、その過程で磨かれたのは「諦めない姿勢」でした。そしてこの経験が、未来を語るときに机上の空論ではない“重み”を与えてくれているのだと思います。
結びに
カーボンクレジットは、理想と現実の狭間で成長している仕組みです。華やかさの裏にある泥臭さを知った今だからこそ、私は強い信念を持って言えます。
「不完全でも動かし続けること」こそが、未来を形づくる唯一の道だと。
これからも挑戦は続きますが、その一歩一歩を共に考え、語り合える仲間が増えることを心から願っています。